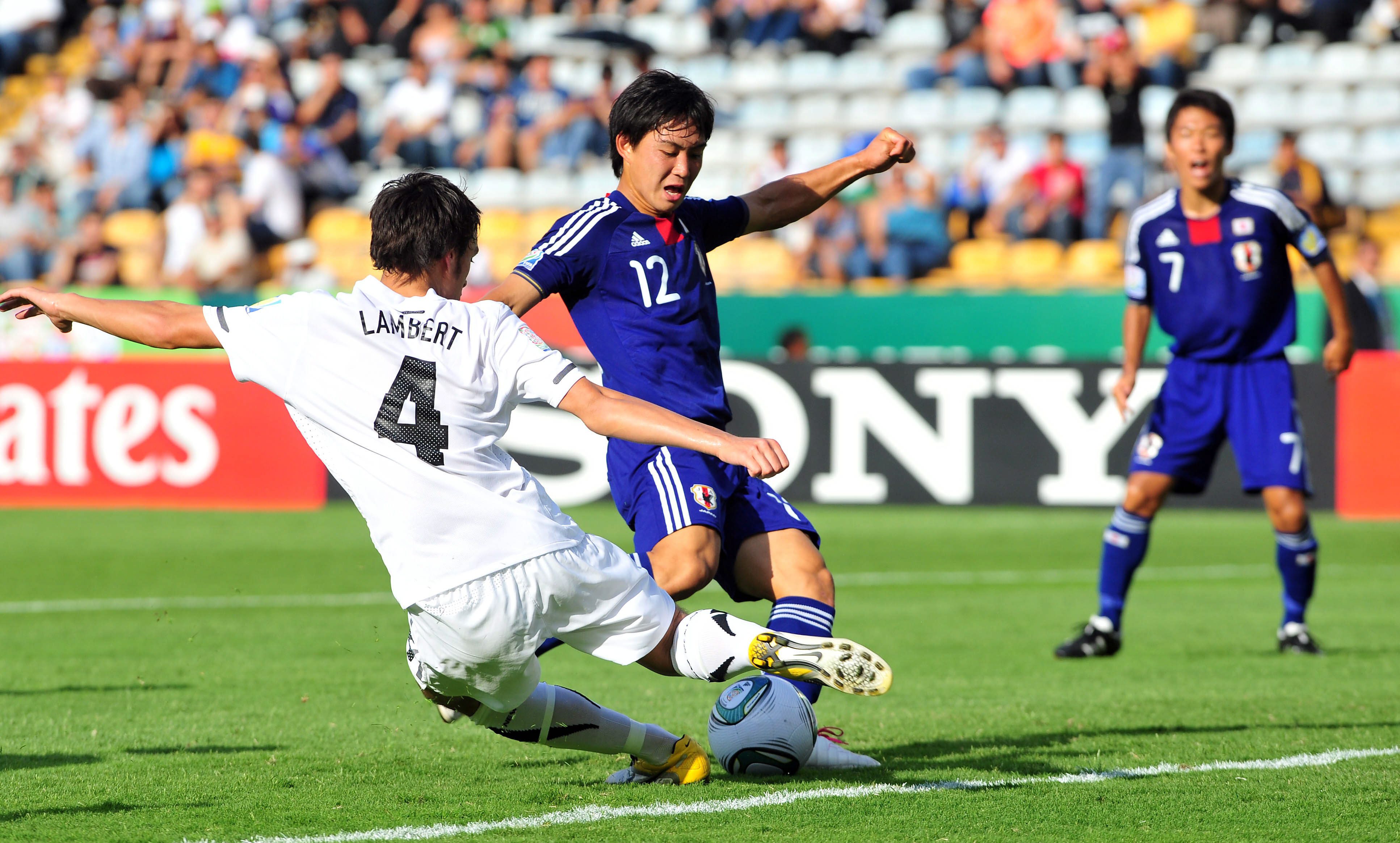Instagramを通じて、1通のメッセージが届く。
「息子はまた元気にサッカーができますか?」
通知に気づいたサッカーJ2・アルビレックス新潟の早川史哉(25)は、自室の天井を眺めながら、しばらく考え込む。
送り主は、急性リンパ性白血病を患ったサッカー少年の母親。

何か力になりたいと思った。ユニホームにメッセージを書いて送ることにした。
「人ごとだとは思えませんでした。自分にできることがあれば何か力になりたいと思って」
自分にできることは、何なのか。
ほんの数年前までは、そんなことを深くは考えなかった。
アスリートとして生きる意義。
今はいつも、自分に問いかけている。

新潟を背負っていくであろう逸材
中学時代から、世代別代表に名を連ねていた。
身長170cmと決して恵まれた体格ではないものの、それを補うだけの頭の良さがあり、あらゆるポジションをこなすことができる。
サポーターの間では知られた存在だった。
地元・新潟市出身で、高校卒業後にプロになる道もあったが「外の世界も見たかった」と、あえて筑波大学へ進学。
サッカーの技量もさることながら、誠実な人柄が、いつも人望につながる。大学では主将も務めた。
卒業後の2016年、中高時代を過ごしたJ1(当時)新潟のトップチームに加入。
大卒ルーキーとして、2月27日の開幕戦でスタメンに抜てきされ順調なスタートを切った。
地元・新潟出身、世代別代表、開幕スタメン。
背番号28のディフェンダー、早川史哉が将来のクラブを背負って立つーー。
サポーターの誰もが、そう思っていた。
「なんで俺が!?」
すぐに息が上がり、疲労感が抜けない。
華々しいデビューからすぐ、体に異変が起きる。
プロ特有の厳しさからくるものだと思い、つらさを我慢していた。
求められるプレーに応えられず、悔しい毎日を過ごした。
リーグ開幕からおよそ2カ月後の4月25日、リンパ節に腫れが見られ、新潟市内の病院で検査。
診断結果は「急性リンパ性白血病」。
「なんで俺が!?」
当時を振り返って、早川はそう述懐した。
それまでの人生、大きな病気を患ったことなどなかったし、アスリートとして体には常に気をつかってきた。
そんな中で、突然襲ってきた白血病の不条理さ。
順調に思われたキャリアは、突如として暗転した。
その一方で、どこかホッとしている自分もいた。
「そりゃ俺の体、動かないよな」
自分がプロのレベルについていけないのではなく、病気のせいだったのだと。
サッカーではひたむきにプレーして周りの模範となる。
インタビューではメディアの期待以上のコメントを返す。
常にチームの中心として活躍してきた早川にとって、自身が納得できないプレーをすることが、何よりも悔しかった。
そこから2カ月間、治療を受けながらさまざまなことに思いを巡らせる。
「サッカー選手を辞めて、教員になる道もあるかもしれない…」
大学時代に取得した教員免許。サッカー以外の"別の道"も考えた。
それでもたどり着いた答えは「もう一度大好きなクラブ、アルビレックス新潟に戻りたい」。
自分の気持ちを再確認し、復帰を前提として白血病公表に踏み切った。
「つらい治療が他人に分かるわけがない」
抗がん剤治療をはじめとした闘病生活は、どこまでも過酷だった。
ある日、風呂で頭を洗っていると排水溝が真っ黒になっていた。
自分の髪の毛だった。
あまりのショックに、その場で嘔吐した。
その後も食欲がなくなり、吐き気や悪寒に襲われる日々が続いた。
抗がん剤や放射線による治療は、骨がもろくなったり、大腿骨が壊死したりする可能性がある。
特にアスリートにとっては、大きなリスクだ。
しかしプロとして復帰する以前に、一人の人間として"今日を生きる"という覚悟。一日一日を必死に過ごした。
骨髄バンクを通じてドナーが見つかり、11月には骨髄移植(造血幹細胞移植)手術を実施。
だが検査をしても、快方に向かう兆しが見えない。
闘病生活にいら立ち、焦りを覚え、肉体的にも精神的にも不安定な状態が続く。
誰もが認める人格者とはいえ、性格がゆがんだ。
「このつらい治療が他人に分かるわけがない」。そう思った時期もあった。
周囲の支えと最善の選択
それでも家族をはじめ、周囲の支えが早川を救う。
母は毎日のように病院に通い、病気と闘う息子に寄り添った。
チームメートはもちろん、全国各地の友だちが新潟の病院まで駆け付けた。
医師はプロ復帰を視野に、リスクが少なくなるように治療を工夫した。
新潟サポーターをはじめ、全国から激励のメッセージが寄せられ「早川史哉選手支援基金」も設立された。
クラブは毎試合、背番号28・FUMIYAのユニホームをベンチに掲げた。
スタジアムには毎試合、ピッチにいない早川の応援歌が響き渡った。
「周りの人たちの温かい言葉や支援、そして自分にサッカーをしたいという強い気持ちがあったからこそ、白血病に立ち向かうことができました」
17年1月10日、クラブは早川との契約凍結を発表。
本人・家族・クラブが協議し、治療に専念するために導き出した答えだった。
「それが僕にとって最善の選択でした」
病の寛解、そして復帰に向けて着実にステップを踏みながら、一歩一歩前進する。
周囲の温かい言葉を背に、白血病は少しずつ、快方に向かう。
原点に立ち返る
アスリートとしてのリハビリも、始められるようになった。
軽いジョギングから運動を始め、徐々に負荷を高める。
体は思ったよりも動くようになった。
しかしその分「先」を見てしまうことも多くなった。
プロに戻れるのだろうかーー。

U-18の練習に参加するようになった。
「プロ」としての立場から後輩にアドバイスを送る一方で、自分の体が思うように動かないという現実にも直面する。
練習による筋肉の痛みも、病気が再発したのではないかと常に不安が付きまとう。
それでも、やるしかなかった。
高校生との練習で、足を引っ張りながらも懸命にプレーした。
まだ要領は良くなくても、ひたむきにプレーする高校生たちを見て、勇気をもらった。
18年7月「ミスター・アルビレックス」本間勲の引退試合に早川の姿があった。
地元出身で、現役時代の大半を新潟で過ごした本間は、早川にとってまさに「手本」のような存在。
そんな先輩の晴れ舞台で、2年ぶりにホーム・デンカビッグスワンスタジアムのピッチに帰ってきた。
試合中、早川の笑顔は絶えることがなかった。
まるでサッカー少年の頃に戻ったかのように、純粋にボールを追い掛けた。
「えがおのヒミツ」
18年11月。
クラブは医師や家族を含めた協議の末、早川との契約凍結解除を発表した。
「白血病になったアスリートとして、病気について多くの人に伝えたい」
本格的な復帰が見えた中、プロとしての使命感も芽生え始める。
助かる人もいれば、そうではない人もいる。
病棟では、自分と同じような悩みを抱える患者をたくさん見てきた。
ドナーに生かされた命。
メディアに露出するアスリートとして、多くの人に白血病の実情を伝えたい。
オフシーズンには、講演会や出前授業など、あらゆる所に顔を出して病気について語った。

新潟市の鏡淵小学校では、児童に交じってサッカーをした後、特別授業も行った。
テーマは「えがおのヒミツ」。
"お礼"として、児童から贈られた合唱の最中には、涙を流す場面もあった。

闘病中のブログには、病気になってから涙もろくなったとつづった。
たくさんの人から温かい言葉をもらい、人の優しさを改めて感じることが増えた。
「えがおのヒミツ」ーー。
早川にとって、それはまさに周囲の支えだった。

19年2月12日。
競技こそ違うが、競泳の池江璃花子が白血病と診断されたことを公表。
クラブ公式サイトを通して、早川はすぐにコメントを発表した。
「池江選手に温かい優しさをたくさん与えてほしいと思います。そういう想いが必ず池江選手の力になると思っています。それは、僕自身も感じてきたことでもあるからです」
「まずは一人の人間として元気になってくれることを僕は願っています」
復帰以前に、まずは生き抜くこと。
つらい闘病生活を送ってきた、同じアスリートだからこその言葉だった。
自分らしく、ただひたむきに
ただ、"白血病のアスリート"で終わるつもりはない。
試合に出場する。レギュラーを取り返す。さらに、日本代表に選ばれる。
選手としての活躍は、同じような病の人たちを勇気づけることにもつながる。
スポーツ選手に限らず、病気などで一度離脱してしまうと、再び順調なキャリアを歩むことは難しいといわれる。
しかしそれは同時に、新たなチャレンジの始まりでもある。
自らの競技人生を通じて、そう示すことができるのも、アスリートだからこそだ。
オフシーズンの自主トレ。
再びプロの舞台で輝くために、過酷なフィジカルトレーニングをこなす。
チームメートとボールを蹴る時間では、自然と笑顔がこぼれる。

「復帰してから、サッカーというスポーツをする喜びを今まで以上に感じています」
過酷な合宿の中でも、早川の笑顔は変わらなかった。
充実感に満ちた表情でボールを追い掛ける。

練習試合では、出場した時間に2失点。まだまだ課題も多い。
「長い距離を走った後にプレーするようなフィジカル能力が、今の自分に一番足りないところ」
約1年半の闘病を経て、体の状態も理解している。

それでも頑張れるのは、あのときたどり着いた「もう一度大好きなクラブでプレーがしたい」という気持ちと「温かい言葉を掛けてくれた人たちにスポーツの力で恩返ししたい」という思い。

だからこそ、ピッチに立つ。
笑顔で、ひたむきに、自分らしく。再びピッチへ。
早川史哉はこれからも、前を向いて歩く。
【取材・撮影・文=加藤貴大(LINE NEWS編集部)】